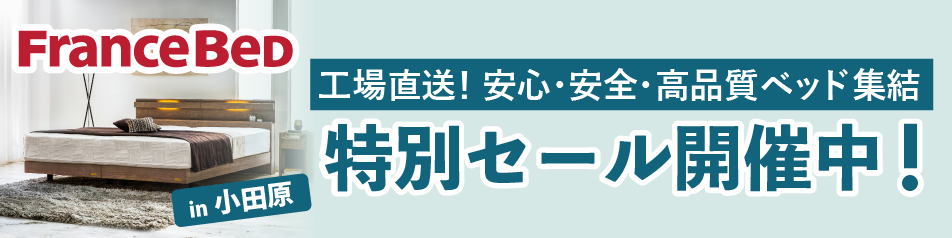.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
深い睡眠で毎日を快調に!熟睡のメカニズムとぐっすり眠るための方法
公開日:2025.08.30(Sat)
「しっかり寝たはずなのに疲れが残る」そんな悩みを抱えていませんか?
睡眠時間は十分でも、眠りの深さが足りないと疲労が抜けないことがあります。また、睡眠計測アプリで浅い眠りが多いと気づき、どうすれば熟睡できるのか知りたい方も多いでしょう。
本記事では、深い睡眠の基礎知識や、熟睡して心身を回復させるためのコツを分かりやすく紹介します。
深い睡眠とは?睡眠のメカニズム
人の睡眠には2つの種類があります。
レム睡眠は身体は休んでいるが脳が活発に働き夢を見る浅い眠りです。一方、ノンレム睡眠は脳の休息にあたる深い眠りです。
通常、入眠後は約90分周期でノンレム睡眠とレム睡眠が交互に現れ、一晩に4~5回のサイクルを繰り返します。このうち深い睡眠とは、ノンレム睡眠の中でも特に深い段階を指し、眠り始めの前半に集中的に出現するのが特徴です。
深いノンレム睡眠から夜の睡眠は始まり、朝に近づくにつれて浅いノンレム睡眠が増えていきます。同時にレム睡眠の割合も後半ほど長くなり、明け方には全体的に浅い眠りが中心になります。
深い睡眠時には脳波がゆっくり大きくなるため徐波睡眠とも呼ばれ、外から揺さぶっても簡単には起きないほど深い眠りの状態です。深いノンレム睡眠中には脳の活動が大幅に低下し、昼間に酷使した大脳を冷却・休ませて集中的に回復させています。
一方、レム睡眠中は全身の筋肉が力を抜いて休んでいる状態ですが、脳は比較的活発で夢を見たり血圧・脈拍が変動したりします。レム睡眠は身体のエネルギーを節約しつつ、心身を覚醒へと準備させる役割があり、ノンレム睡眠とは質的に異なる「浅い眠り」です。
このように私たちの眠りは深い睡眠と浅い睡眠がリズミカルに入れ替わりながら進行していきます。
深い睡眠が身体・脳にもたらす効果
深い睡眠には心身の疲労を取り、脳と身体をリフレッシュさせる大切な役割があります。
眠りに入って最初の深いノンレム睡眠の時間帯には、成長ホルモンの分泌が特に高まります。成長ホルモンは子どもでは骨や筋肉の発達を促し、大人にとっては細胞の修復や新陳代謝の促進を担うホルモンです。
深くぐっすり眠ることで身体のダメージ修復や筋肉の疲労回復が進み、肌の新陳代謝が活発になるなど、健康維持に欠かせない働きがあります。
また、質の良い睡眠は自律神経のバランスを整えて心臓や胃腸の負担を軽減し、日中の体調を整える効果もあります。十分に深い睡眠がとれると生活リズムが安定し、体内のホルモン分泌も正常に保たれやすくなるため、肥満・高血圧・糖尿病といった生活習慣病のリスク低下につながることが分かっています。
さらに睡眠不足が続くと食欲を抑えるホルモンが減少し、逆に食欲を増進させるホルモンが増えると報告されています。その意味でも熟睡は太りにくい体づくりに役立つといえるでしょう。
十分に深い睡眠をとることはメンタルヘルスの面でも重要です。夜ぐっすり眠れていれば脳の神経細胞も回復し、ストレス耐性が高まったりポジティブな思考を保ちやすくなったりします。
実際に、良質な睡眠は不安感や憂うつ状態の予防につながることが知られています。しっかり熟睡できた翌朝は頭が冴えて気分も安定し、日中の集中力や作業効率も向上します。
反対に深い睡眠が不足すると、「寝たのに疲れが取れない」「日中にぼんやりしてミスが増える」などの不調が現れやすくなるため注意が必要です。
加齢による深い睡眠の減少
年齢を重ねるにつれて「昔より熟睡できなくなった」と感じる方が多くなります。
実は、深い睡眠の量は加齢とともに減少することが科学的に示されています。一般に高齢になるほど睡眠は浅く断片的になり、中高年では若い頃に比べて深いノンレム睡眠の時間が短くなる傾向があります。
睡眠の途中で目が覚めてしまう中途覚醒も加齢とともに増えるため、どうしても全体的な睡眠の質が低下しがちです。「歳を取ると仕方がない」と言われますが、深い睡眠が減るのは生理現象の一つではあるものの、本人の体感としては熟睡感の乏しさに繋がります。
深い睡眠はどのくらい減るのか
例えば、10代の若者の深い睡眠時間を100%とすると、40代後半ではその約6割程度に、70代ではわずか2割程度にまで落ち込むという報告もあります。
加齢により浅いノンレム睡眠(うとうとした眠り)の占める割合が増え、深い眠りが大幅に減少するためです。その結果、中高年以降では「ぐっすり眠れない」「睡眠時間は足りているのに疲れが取れない」といった状態に陥りやすくなります。
高齢者特有の睡眠の問題
さらに高齢者特有の要因も熟睡を妨げます。
年を取ると夜間頻尿(トイレに起きる回数の増加)や関節・腰の痛みなど慢性的な症状を抱えることが多く、これらによって睡眠途中で目覚めやすくなります。眠っているつもりでも実際には細切れ睡眠になってしまい、睡眠効率(寝床にいる時間のうち実際に眠れている割合)が下がってしまうのです。
また、体内時計の変化も関係します。加齢に伴い、夜になると分泌される睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌開始時刻が前倒しになる傾向があり、若い頃より早い時間に強い眠気が訪れるようになります。
そのため高齢者は早寝早起きのリズムに移行しやすく、夕方~夜に早い時間にウトウト眠ってしまい夜中に目が覚める、朝は必要以上に早朝に起きてしまう、といったことが起こりやすくなります。
このように加齢による睡眠の変化自体は避けられませんが、生活習慣や環境を工夫することで深い睡眠の減少を和らげることは可能です。
深い睡眠を増やす方法
十分な深い睡眠を得るために、日頃の生活習慣や睡眠環境を見直すことが効果的です。
ここでは熟睡するための具体的な方法をいくつか紹介します。年齢に関係なく実践できるポイントばかりですので、できることから取り入れてみてください。
規則正しい生活リズムを保つ
深い睡眠の土台となるのは体内時計に沿った規則正しい生活です。
平日だけでなく休日も含め、毎日できるだけ同じ時刻に寝起きするよう心がけましょう。人間の体内時計は24時間よりやや長い周期を持つため、朝の太陽光によって毎日リセットする必要があります。
朝起きたらまず日光を浴びる習慣をつけると、体内時計がリセットされ夜に自然な眠気が訪れやすくなります。
逆に夜遅くまで強い光を浴びる生活を続けると、体内時計のリズムが乱れて睡眠時間になっても脳が覚醒してしまいがちです。特に就寝前のスマートフォンやパソコン画面からのブルーライトは睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑制し、深い睡眠を減らしてしまう要因になります。
寝る前の1~2時間は画面を見る時間を減らし、部屋の照明も少し落としてリラックスするようにしましょう。
生活リズムを整える基本は以下の通りです:
- 朝起床したら太陽光を浴びて体内時計をリセットする
- 毎日同じ時間帯に寝て起きる(休日に大幅な寝だめや夜更かしをしない)
- 夜は強い光を避ける(画面や照明のブルーライトに注意し、就寝前は間接照明や暖色系の明かりで過ごす)
適度な運動で睡眠の質をアップ
日中の適度な運動習慣は深い睡眠を促すことが知られています。
ウォーキングや軽いジョギングなど無理なく続けられる有酸素運動を習慣化している人は、寝つきが良く夜間の中途覚醒が少ない傾向があります。さらに、睡眠中の深い睡眠(ノンレム睡眠)の割合も増えることが報告されています。
運動するタイミングも重要で、夕方から就寝3時間くらい前までの時間帯に軽い運動を行うと、一時的に上がった体温が就寝時に下がってスムーズに入眠しやすくなります。
例えば仕事帰りにストレッチやヨガ教室に通う、夕食後に軽く散歩する、といった習慣でも効果的です。ただし、寝る直前の激しい運動は交感神経が高ぶってかえって眠れなくなるため避けましょう。
就寝前の入浴とリラックス
お風呂に入ってリラックスすることも深い睡眠を得る良い習慣です。
寝る1~2時間前にぬるめ(目安として38~40℃)のお湯にゆっくり浸かると、身体の芯(深部体温)が一時的に上昇します。その後、入浴で温まった体が冷めていくタイミングで自然な眠気が訪れ、スムーズに入眠しやすくなります。
忙しい方も、シャワーだけで済ますのではなくできれば湯船に浸かって体を温める習慣をつけると良いでしょう。
入浴後は副交感神経が優位になり心身がリラックスした状態です。このタイミングで軽いストレッチをしたり、柔軟体操やヨガで体をほぐしたりするのも効果的です。寝る前に好きな音楽を聞いたり読書をしたりしてリラックスする時間を持つのもおすすめです。
一方、就寝直前まで仕事のメールチェックや難しい勉強をしていると、脳が興奮状態のままで布団に入ることになり深い睡眠の妨げとなります。
可能であれば就寝前の1時間はパソコンやスマホから離れ、ゆったりとした気分で過ごしましょう。「早く寝なきゃ」と焦ると余計に眠れなくなるため、眠気が訪れるのを待つくらいの気持ちで心と体を解放してあげることが大切です。
どうしても不安や悩み事で頭が冴えてしまうときは、いったん紙に書き出して頭の中から追い出したり、信頼できる人に話したりして心の緊張を和らげてみてください。
快眠のための寝室環境を整える
寝室の環境も熟睡には見逃せないポイントです。
人間は眠りに入るとき体の内部の体温を下げていきますが、周囲の環境が快適でないと深い睡眠が妨げられます。寝室は暗く静かで、自分が心地よいと感じる温度・湿度に保ちましょう。
一般的に、ふとんに入ったときの寝床内の温度は約33℃、湿度は50%程度が快適な環境だとされています。エアコンや加湿器を使って部屋の温湿度を調整し、夏は暑すぎず冬は寒すぎないよう工夫しましょう。
季節別の寝室環境のポイント
特に冬場は布団が冷えていると体が縮こまってリラックスできず、寝つきが悪くなってしまいます。湯たんぽや電気毛布(就寝前に切るタイマー設定にする)などで寝具をあらかじめ温めておくと、布団に入った後に体から熱がスムーズに放散され、深い眠りに入りやすくなります。
反対に夏場は汗による寝苦しさで眠りが浅くならないよう、通気を良くしたり冷却マットを利用したりして、身体がこもった熱を逃がせる工夫が必要です。
寝室の照明は就寝時には真っ暗にするのが理想ですが、真っ暗だとかえって不安な場合は足元に小さな豆電球を点けるなどして工夫しましょう。夜間の物音や生活騒音が気になる方は耳栓を使ったり、静かな音楽・ホワイトノイズを流したりして対策すると安心です。
また、寝室は「眠るための部屋」と割り切り、ベッドの上でスマホを長時間いじったり仕事を持ち込んだりしないようにしましょう。寝室をリラックスできる空間に保つことで、布団に入ったときスムーズに睡眠モードへと切り替えられるようになります。
自分に合った寝具の見直し
寝具(マットレス・枕・ふとん類)の良し悪しも深い睡眠に直結します。
毎晩何時間も身体を預ける寝具は、自分の体格や寝姿勢に合ったものを使用することが大切です。特にマットレスや敷き布団の硬さは重要で、柔らかすぎても硬すぎても熟睡を妨げる原因になります。
マットレス選びのポイント
極端に柔らかすぎる寝具では腰や背中が沈み込んで背骨のS字カーブが崩れ、寝姿勢が不自然になってしまいます。一方、硬すぎる寝具では身体の出っ張った部分に圧力が集中して血流が妨げられ、痛みやしびれで目が覚めることもあります。
適度な硬さで身体をしっかり支えてくれる寝具を選ぶことで、自然な寝姿勢を保ち深い眠りを維持しやすくなります。
掛け布団と枕の選び方
掛け布団についても、重すぎる布団は寝返りを打ちにくく圧迫感で睡眠を浅くする恐れがあります。保温性がありつつ軽く体にフィットする掛け布団が理想です。
寝ている間、人間の身体はコップ一杯分ほどの汗をかくとも言われます。汗や湿気をうまく吸収・発散してくれる素材の寝具を使うことで、寝床内の熱や湿度がこもらず快適さを保てます。
枕も自分に合ったものを使いましょう。人それぞれ首のカーブや肩幅は異なるため、枕の高さ・硬さの好みも違います。理想的な枕は仰向けに寝たときに後頭部から首のすき間をしっかり埋めて支え、立っている時とほぼ同じ自然な角度で頭と首を保持してくれるものです。
高さが合わない枕(高すぎ・低すぎ)は首や肩に負担がかかり、寝苦しさや肩こりの原因になります。試し寝ができる店舗で自分の首にフィットする枕を探してみるとよいでしょう。
寝具の買い替えを検討しよう
現在使っている寝具が自分に合っていないと感じる場合や、長年使用してヘタってきた場合は、思い切って寝具を新調することも検討してください。
近年は各メーカーから様々な高機能寝具が発売されています。例えば、世界的マットレスブランドのシーリーやサータ、シモンズなどからは体圧分散に優れたポケットコイルマットレスが多数展開されており、身体を均等に支えることで寝返りしやすく深い眠りを妨げにくい設計になっています。
また、老舗寝具メーカー昭和西川の「ムアツふとん」に代表されるように、点で身体を支える構造で血行を妨げにくい敷き寝具も人気です。枕では高さを自由にカスタマイズできるタイプや、安定感のある低反発素材の枕なども市販されています。
自分の体型や寝姿に合った寝具を選ぶことで、睡眠の質は格段に向上するでしょう。
寝具選びのチェックリスト:
- マットレスは横になったとき身体が沈み込みすぎず、自然な背骨のカーブを保てる硬さか
- 枕は仰向け・横向きいずれの姿勢でも首・頭をしっかり支え、肩や首筋に負担がかからない高さか
- 掛け布団は季節に合った保温性があり、軽くて身体にフィットするか
- 寝具の通気性・吸湿性は良いか(寝汗や湿気がこもらず快適か)
- 現在の寝具に劣化やへたりがないか(購入から10年以上経過して著しくクッション性が低下していないか)
深い睡眠を妨げる要因と悪習慣
せっかく早寝を心がけても、以下のような悪習慣があると深い睡眠が阻害されてしまいます。熟睡のために、次のポイントにも注意しましょう。
就寝前のスマホや強い光刺激
夜遅くまで明るい照明の下で過ごしたり、寝る直前までスマホ画面を見ていたりすると、脳が昼間と勘違いしてしまい睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌が妨げられます。
特にスマートフォンやタブレット、PCなどの画面が発するブルーライトは体内時計を遅らせ、深い睡眠の大敵です。
寝る前の1~2時間はできるだけ画面を見る時間を減らし、代わりにリラックスできる行動に置き換えてみましょう。どうしてもスマホを使う必要がある場合は、ブルーライトカットのフィルターを使用したり画面の明るさを落とす工夫をしてください。
就寝時は部屋の電気を消して真っ暗にするのが理想ですが、難しい場合は豆電球程度の微かな明かりに留め、脳への刺激を最小限に抑えましょう。
アルコールの摂取(寝酒)
「お酒を飲むとぐっすり眠れる」と思っていませんか?
確かにアルコール(寝酒)は飲んでから寝付くまでの時間を短縮し、入眠直後の深い睡眠を一時的に増やす効果があります。しかしその作用は持続しません。
アルコールが分解され始めると興奮物質が放出されるため、睡眠後半には深い睡眠が減少して浅い睡眠が増加し、夜中に目が覚めやすくなってしまいます。飲酒量や個人差に関係なく、アルコールは睡眠途中の中途覚醒を増やすことが報告されています。
つまり、一見寝つきが良くなったように感じても、アルコールは睡眠全体の質を悪化させてしまうのです。特に深酒をすると一時的に昏睡に近い深い眠りに陥りますが、その後すぐに浅い眠りへ移行し断片的な睡眠になります。翌朝に「二日酔いでだるい」「熟睡感がない」と感じるのはこのためです。
ぐっすり眠るためには寝酒に頼らず、上述した入浴やストレッチなど健康的なリラックス法で眠気を誘うようにしましょう。どうしても飲みたい場合は寝る数時間前までの適量に留め、就寝直前の飲酒は避けることが賢明です。
カフェイン・喫煙(ニコチン)の刺激
カフェインには強い覚醒作用があり、体質によっては摂取後5~6時間ほど効果が持続します。
コーヒーや紅茶、緑茶、コーラ、チョコレートなどに含まれるカフェインを夜遅くに摂ると、脳が刺激されて寝つきが悪くなり深い睡眠が減ってしまいます。熟睡したい方は、夕方以降のカフェイン摂取を控えるようにしましょう。
特に就寝前のコーヒーや濃いお茶は避け、水や白湯などカフェインレスの飲み物に切り替えるのがおすすめです。
喫煙習慣のある方も注意が必要です。タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激する作用があり、就寝前の一服は脳を覚醒状態にしてしまいます。
寝る直前だけでなく、夕食後のくつろぎタイムについ喫煙してしまうという人は、寝つきを良くするために禁煙・節煙を心がけることが大切です。ノンニコチンのリラックス用ハーブティーなどに置き換えるのも良いでしょう。
精神的ストレス・緊張
ストレスや不安・緊張も深い睡眠を妨げる大きな要因です。
心理的なストレスを感じていると交感神経が優位になり、布団に入っても脳が休まらず眠りが浅くなってしまいます。心配事や明日の予定など考えだすとキリがなく、ますます眠れなくなるという悪循環に陥ることもあります。
対策としては、就寝前に悩み事を考えない工夫が有効です。気がかりな用件は寝る前にメモに書き出して頭から追い出してしまいましょう。また、軽い読書やヒーリング音楽を聴く、アロマを焚いてみるなど、自分なりのリラックス法で精神を落ち着かせてから寝床に入るようにしてください。
ストレスフルな日々が続いて慢性的に眠れない場合は、一人で抱え込まず専門医に相談することも検討しましょう。不眠が続くとさらにメンタルヘルスが悪化する恐れもあるため、早めの対処が肝心です。睡眠専門のクリニックでは認知行動療法など薬に頼らない治療法も提供されています。
必要に応じてプロの力を借りつつ、日頃からストレスを溜めすぎない生活を心がけることが大切です。
まとめ:深い睡眠で心身のコンディションを整えよう
深い睡眠は脳と身体の重要な休息時間であり、疲労回復やホルモン分泌、記憶の整理など様々な役割を担っています。睡眠時間だけでなく眠りの深さを意識することが大切です。
加齢とともに深い睡眠は減少しますが、生活習慣の工夫次第で睡眠の質は向上させることが可能です。年齢を理由に諦めず、できる対策から試してみましょう。
規則正しい生活(毎朝の太陽光・決まった就寝起床時刻)や適度な運動習慣は深い睡眠を促します。忙しくても朝昼のリズムを整え、体を適度に動かす時間を作りましょう。
寝る前の習慣を見直し、入浴やストレッチなどリラックスできる行動を取り入れてください。反対に、就寝前のスマホ・PC、カフェイン摂取、喫煙、飲酒などは熟睡を妨げるため控えましょう。
寝室環境と寝具も重要です。静かで暗い快適な寝室を整え、自分に合ったマットレス・枕を使うことで、体への負担が減り深く眠りやすくなります。寝具は定期的に見直し、必要に応じて買い替えることも検討しましょう。
毎日の眠りの質を少しずつ改善していくことで、「朝までぐっすり眠れた!」という実感が得られるはずです。深い睡眠は一朝一夕で劇的に増えるものではありませんが、紹介したポイントを継続することで徐々に効果が現れてきます。
眠りの質が向上すれば、日中のパフォーマンスや健康状態も驚くほど良くなります。ぜひ今日からできることに取り組み、深い睡眠で心身のコンディションを整えていきましょう。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。