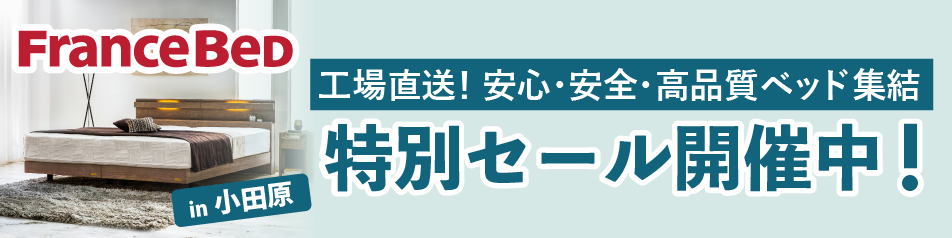.png?w=660&h=900)
ベッド・マットレスのこと
睡眠が浅いのはなぜ?原因と対策を徹底解説!ぐっすり眠るためのポイント
公開日:2025.08.30(Sat)
「夜中に何度も目が覚める」「夢ばかり見て熟睡した気がしない」という経験はありませんか?睡眠時間は十分なのに疲労感が残り、日中もぼんやりしてしまう。このような悩みを抱える方は実に多いのです。
厚生労働省の調査では、約5人に1人が睡眠の質に満足できていないことが分かっています。本記事では「睡眠が浅い」状態の原因と対処法を分かりやすく解説します。
原因を正しく知って効果的な改善策を実践すれば、ぐっすりと深い眠りを手に入れることができます。
睡眠が浅いとはどういう状態?
まず、「睡眠が浅い」とはどのような状態なのかを整理してみましょう。
睡眠の仕組みを知ろう
睡眠には大きく分けて2つの状態があります。
レム睡眠:体は休息しているが脳が活動している浅い眠り ノンレム睡眠:脳も休息する深い眠り
この2つが約90分周期で交互に現れます。通常、寝入り直後から深いノンレム睡眠が現れて脳と体をしっかり休めます。その後レム睡眠に移行するサイクルを繰り返すのです。
しかし、何らかの要因で深い眠り(ノンレム睡眠)に十分移行できずにレム睡眠ばかりの状態になると、「眠りが浅い」と感じるようになります。
浅い眠りでは脳が覚醒に近い状態のため、ちょっとした物音や光で目が覚めやすくなります。朝まで熟睡したという満足感も得にくくなってしまうのです。
浅い眠りのサイン
睡眠が浅い人によく見られるサインをチェックしてみましょう。
中途覚醒が多い 夜間に何度も目が覚めてしまいます。トイレに起きたり、物音で目覚めたりしやすい状態です。
夢を頻繁に見る 朝起きたときに複数の夢をはっきり覚えていることが多くなります。夢そのものは誰でも見ますが、何度も夢を見て記憶している場合は睡眠が浅い可能性があります。
熟睡感がない 睡眠時間は足りているのに「ぐっすり眠れた」と感じられません。疲労感やだるさが残り、朝すっきり起きられない状態です。
このように、睡眠が浅い状態とは深い睡眠が不足したアンバランスな睡眠といえます。「布団に入っているのに全然寝た気がしない」「常に寝不足のようだ」という場合、それは睡眠の浅さが原因かもしれません。
眠りが浅くなる原因は?
では、なぜ深く眠れずに浅い眠りになってしまうのでしょうか。主な原因として、ストレスや生活習慣の乱れ、生理的な変化、睡眠環境の問題など様々な要因が考えられます。
過度なストレス・心理的要因
日中の強いストレスや緊張、不安などの心理的要因は浅い眠りの大きな原因です。
ストレスがかかると自律神経のうち交感神経(活動時に優位になる神経)が夜になっても高ぶったままになります。その結果、心拍数や体温が下がりにくくなり、リラックスできません。
寝つきが悪くなったり夜中に目覚めやすくなったりしてしまいます。また、仕事や人間関係の悩み事を考えながら床につくと脳が興奮状態となり、眠りにつくまでに時間がかかるだけでなく睡眠も浅くなりがちです。
さらに不安障害やうつ病などメンタルヘルスの不調がある場合も睡眠が浅くなりやすいとされます。心当たりがある場合は、ストレスケアや必要に応じ専門医への相談も検討しましょう。
生活習慣の乱れ
不規則な生活リズムも眠りを浅くする一因です。
平日と休日で就寝・起床時刻が大きく異なったり、夜更かしや徹夜で生活リズムが乱れていると、体内時計がずれて睡眠のサイクルが不安定になります。その結果、夜になかなか寝付けなかったり睡眠周期が乱れて浅い眠りが増えることがあります。
また、就寝前の過ごし方も重要です。寝る直前までスマートフォンやパソコンの画面を見ていると、画面から発せられる強い光(ブルーライト)が脳を刺激します。睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を妨げ、浅い眠りの原因になるのです。
厚生労働省も寝る前の明るい光は入眠を妨げ睡眠を浅くする可能性があると注意を呼びかけています。
浅い眠りを招く主な生活習慣
- 就寝前のスマホ・PC作業(脳への強い光刺激で睡眠ホルモン減少)
- 深夜の飲食(胃腸への負担やカフェイン摂取による覚醒作用)
- 極端な夜型生活・昼夜逆転(体内時計の乱れで睡眠リズムが崩れる)
こうした生活習慣を見直すだけでも、睡眠の質が向上して浅い眠りの改善につながる場合が多いです。
加齢による睡眠の変化
年齢を重ねるにつれて眠りが浅くなることは、生理的にもある程度仕方のない側面です。
一般に、加齢に伴い深いノンレム睡眠の割合が減少し、睡眠全体が浅く短くなる傾向があります。例えば中高年の方は若い頃に比べて夜間に何度も目覚める中途覚醒が増えたり、朝早くに目が覚めてしまう早朝覚醒が起こりやすくなります。
「歳のせいか夜中に目が覚めやすくなった」というのは珍しいことではありません。
また、高齢になると必要な睡眠時間自体が短くなることも知られています。厚労省のデータによれば、45歳で平均約6.5時間、65歳以上では6時間程度と、加齢により生理的な睡眠時間は次第に短くなります。
にもかかわらず若い頃と同じだけ寝ようと長時間布団に入っていると、かえって眠りが浅くなり夜中に何度も目覚める原因になります。これは必要以上に長く寝床に留まることで睡眠効率が下がり、浅い眠りが増えてしまうためです。
中高年の方は「無理に長く寝ようとしない」ことも深く眠るコツと言えるでしょう。
更年期・ホルモンバランスの変化
特に40代以降の女性の場合、更年期におけるホルモンバランスの急変が睡眠の浅さに直結するケースがあります。
更年期に入ると卵巣機能の低下により女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少します。この変化が脳内の睡眠中枢に影響を与え、睡眠の質を低下させると考えられています。
実際に更年期の女性には「寝つきにくくなる」「夜中に何度も起きてしまう」「朝早く目が覚める」といった不眠症状が増えることが知られており、浅い眠りになりがちです。
加えて、更年期にはほてりや発汗(ホットフラッシュ)などの自律神経症状が就寝中に起こることもあります。夜中に大量の汗をかいて目覚めてしまい、着替えているうちに目が冴えて眠れないという悪循環に陥ることもあります。
こうした更年期由来の睡眠障害については、婦人科でのホルモン補充療法(HRT)や漢方治療などで改善が期待できる場合もあります。もし更年期の症状が思い当たる場合は、一人で抱え込まず専門医に相談してみましょう。
睡眠環境の問題
睡眠環境が不適切なために熟睡できないケースも多々あります。
明るさや音の影響 寝室の明るさや音は浅い眠りの大敵です。人間は光に反応して目覚める性質があるため、夜間に街灯や部屋の明かりが差し込んでいると眠りが浅くなってしまいます。
また、時計の秒針や冷蔵庫の駆動音、同居家族のいびきなど小さな物音でも、繊細な方は目が覚めてしまうでしょう。できるだけ暗く静かな寝室になるよう工夫が必要です。
寝具の重要性 見落とせないのが寝具(ベッド・マットレス・枕など)の影響です。自分に合わない寝具は身体に負担をかけ、睡眠中の無意識の寝返りを妨げてしまいます。
その結果、腰や肩に痛み・違和感が生じて眠りが浅くなることがあります。実際、敷布団やマットレスが硬すぎたり柔らかすぎたりすると寝返りしづらくなったり血行が悪くなったりして、深い眠りの妨げになると報告されています。
特に長年使ってへたった寝具は要注意です。身体を十分に支えられず寝姿勢が崩れてしまい、夜中に何度も目覚める原因になりえます。
「夜中に腰痛で目が覚める」「枕が合わず何度も起きてしまう」という場合は、思い切って寝具を見直すことも検討しましょう。
アルコール・カフェイン・喫煙の影響
就寝前に摂取するアルコールやカフェインなどの嗜好品も浅い睡眠の原因となります。
アルコールの落とし穴 適量のアルコールはリラックス効果で一時的に寝つきを良くすることがありますが、その後の睡眠はむしろ浅くなりやすいことが分かっています。
厚生労働省の睡眠指針でも「寝酒」は中途覚醒を増やし熟睡感を損なうと警告されています。お酒を飲んで眠っても夜中に喉の渇きやトイレで目覚めたり、浅い眠りになってしまうのです。
カフェインとニコチンの覚醒作用 カフェインについては、就寝前の摂取で浅い眠りの原因となります。コーヒーや緑茶だけでなくエナジードリンクやチョコレートにもカフェインは含まれるため、夕方以降は控えるのが無難です。
また喫煙も問題で、ニコチンには覚醒作用があるため就寝前の喫煙は入眠を妨げ、睡眠を浅くするとされています。
その他の要因
上記のほかにも、慢性的な身体疾患や服用中の薬剤が睡眠を浅くしている場合もあります。
例えば、睡眠中に呼吸が何度も止まってしまう睡眠時無呼吸症候群や、脚のむずむず感で眠れないむずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)などの睡眠障害が潜在していると睡眠の質が低下します。
これらの疾患があると、いくら環境を整えても熟睡が難しいため、専門医による治療が必要です。また一部の降圧薬など副作用で不眠を来たす薬もあります。思い当たる場合は主治医に相談するとよいでしょう。
浅い眠りが続くことによる影響・リスク
「眠りが浅いくらい大したことない」と思うかもしれませんが、浅い睡眠が慢性化すると心身に様々な悪影響が現れます。
深い睡眠が不足すると十分な休息や体の修復ができないため、日中のパフォーマンス低下や体調不良につながります。
日中の眠気・集中力低下
浅い眠りが続くと夜間に脳と体の疲労が十分取れません。その結果、日中に強い眠気に襲われたり、頭がぼんやりして集中力や判断力の低下を感じるようになります。
仕事でミスが増えたり、車の運転中に一瞬寝落ちしてしまう(マイクロスリープ)危険性も高まります。本人は眠っているつもりでも熟睡できていないと脳が休めていないため、起きてからの活動に支障をきたすのです。
情緒の不安定・イライラ
睡眠の質の低下はメンタル面にも影響します。慢性的に熟睡できない状態が続くと、イライラしやすくなったり感情のコントロールが難しくなります。
些細なことで怒りっぽくなったり、気分の落ち込み(抑うつ傾向)が現れることもあります。不眠とメンタル不調はお互いに悪影響を及ぼし合うため、浅い眠りを放置するとストレス耐性の低下や不安・うつ症状の悪化につながる恐れがあります。
身体の不調・生活習慣病リスクの増加
体がしっかり休まらないと身体的な不調も出てきます。睡眠不足が続くと自律神経やホルモンバランスが乱れ、免疫力の低下や高血圧・血糖値の上昇などが生じやすくなります。
その結果、風邪や感染症にかかりやすくなったり、長期的には糖尿病や心臓病など生活習慣病のリスクを高める可能性が指摘されています。
実際、睡眠が慢性的に不足した人は十分眠れている人に比べて肥満や糖代謝異常、高血圧などを発症しやすいとの研究報告もあります。
生活の質(QOL)の低下
以上のように、浅い睡眠がもたらす影響は幅広く、生活の質(QOL)を大きく低下させてしまいます。
毎日熟睡できず疲れや不調を抱えた状態では、仕事や家事、趣味を十分に楽しむ余裕もなくなってしまいます。「よく眠れない」という悩み自体が心理的ストレスとなり、更なる睡眠悪化を招くケースもあります。
健康で充実した日々を送るためにも、浅い眠りの状態は早めに改善することが望ましいでしょう。
浅い眠りを改善し熟睡するための対策
眠りの浅さに悩んでいる方も、適切な対策を講じることで睡眠の質を改善し、深い眠りを取り戻すことができます。ここでは今日から実践できる具体的な改善策を紹介します。
規則正しい生活リズムを整える
深い睡眠の土台となるのは、規則正しい体内時計のリズムです。
不規則な睡眠習慣を改め、毎日できるだけ同じ時間に寝起きするよう心がけましょう。平日だけでなく休日も起床時間が大きくズレないようにすることが大切です。
「昼は太陽光を浴びて活動し、夜になったら眠る」という人間本来のリズムを意識してください。朝起きたらカーテンを開けて朝日を浴び、朝食をしっかり摂ることで体内時計がリセットされます。すると夜は自然と眠気が訪れやすくなります。
昼間に体を適度に動かし、日中に長時間うたた寝しないことも夜の熟睡に繋がります。昼寝する場合は15時より前に30分以内にとどめましょう。
就寝前の過ごし方を工夫する
夜はリラックスして眠りの準備をする時間です。就寝前の行動を見直し、脳と体がスムーズに睡眠モードへ移行できるようにしましょう。
強い光を避ける 寝る1時間前以降はスマホやパソコン、テレビの画面を見るのは控え、部屋の照明も少し落としてみましょう。明るい光を浴びると脳が昼間と勘違いして眠りが浅くなってしまいます。
代わりに音楽を聴いたり読書をするなど穏やかな時間を過ごしてください。
カフェイン・アルコールを控える 夕食後から就寝前にかけてのカフェイン摂取はできるだけ避けます。どうしても飲み物が欲しい場合はカフェインレスのハーブティーやホットミルクがおすすめです。
また、寝酒の習慣がある方は注意が必要です。アルコールは一時的に入眠を助けますが、後半の睡眠が浅くなり疲労回復を妨げます。眠る前のお酒は控え、どうしても飲みたい場合は就寝2時間以上前までに適量に留めましょう。
リラックスできる習慣を 就寝前の緊張を解きほぐす工夫も大切です。例えばぬるめのお湯(40℃前後)にゆっくり入浴すると体が温まり、その後体温がスッと下がるタイミングで眠気が訪れやすくなります。
寝る30分~1時間前の入浴は深い睡眠を増やす効果があることが報告されています。また、軽いストレッチや深呼吸、アロマ(ラベンダーなど鎮静作用のある香り)を取り入れるのも良いでしょう。
自分がリラックスできるルーティンを見つけて続けることで、「これをすると眠くなる」という習慣化が期待できます。
睡眠環境を整える
睡眠環境は熟睡の質を左右します。寝室の環境を今一度チェックしてみましょう。
適切な温度・湿度 夏は暑すぎず、冬は寒すぎない快適な温度を保ちます。一般的に寝室の温度は約25℃前後、湿度は50%前後が快眠に適するとされます。
エアコンや加湿器を活用してみましょう。また、寝具内(布団の中)の温度は33℃前後が理想と言われています。手足が冷えて眠れない場合は靴下や湯たんぽで温め、逆に暑くて眠れない場合は通気性の良い寝具や夏向け素材で涼しくするなど調整します。
静かで暗い部屋 睡眠時には可能な限り音と光を遮断します。どうしても周囲の物音が気になる場合は耳栓やホワイトノイズマシン(自然音など一定の音で他の音をマスキングする装置)を試してみましょう。
光については遮光カーテンやアイマスクの利用がおすすめです。就寝中にトイレへ行く場合に備えて足元灯を付ける場合でも、暖色系の弱い明かりにすると覚醒しにくくなります。
寝具の見直し 自分の体に合った寝具を使うことは、深い眠りの重要な条件です。マットレスは硬すぎても柔らかすぎても体に負担がかかるため、体圧分散に優れたほどよい硬さのものを選びましょう。
高品質なマットレスは、寝返りがしやすく体へのフィット感も高いため睡眠中の不快感を減らしてくれます。枕も高さや素材が合っていないと首や肩のこわばりで途中覚醒の原因になります。
高さ調整のできる枕や、横向き寝が多い人向けの硬めの枕など、自分の寝姿勢に合ったものを選びましょう。寝具は実際に試してみるのが一番ですので、可能であれば寝具専門店で寝心地を確認してみてください。
適度な運動習慣を取り入れる
日中の適度な運動は夜の深い眠りを促進する効果があります。
身体を動かすことで副交感神経の働きが良くなり、夜に自然な眠気が訪れやすくなるのです。実際、定期的に運動している人は中途覚醒が減少し、睡眠が安定して熟睡感が高まるという報告があります。
ウォーキングや軽いジョギング、ヨガ、ストレッチなど無理のない範囲で構いませんので継続してみましょう。
ただし、就寝直前の激しい運動は逆効果です。寝る寸前に心拍数が上がると却って脳が冴えてしまい入眠を妨げます。運動は遅くとも寝る2~3時間前までに済ませ、夜はリラックスできる軽めのストレッチ程度に留めてください。
必要に応じて専門医に相談する
様々な対策を試しても浅い眠りが改善しない場合や、日中の強い眠気・体調不良が続く場合は、一度専門の医療機関で相談してみましょう。
睡眠専門医や精神科医に相談することで、隠れた睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、不眠症など)の有無を調べ適切な治療につなげることができます。
例えば睡眠時無呼吸症候群であればCPAP療法(持続陽圧呼吸)による睡眠の質向上、むずむず脚症候群であれば薬物治療、といった専門的アプローチが有効です。
また、ストレスや不安が強い場合には睡眠導入剤や抗不安薬の処方が一時的に助けになることもあります。医師と相談しながら、根本的な原因にアプローチしていきましょう。
睡眠の悩みは放置せず、早めの対応が肝心です。深く眠れない日々が続くと心身の不調に直結しますから、「おかしいな」と思ったら生活習慣の改善と並行して専門家の力も借りるようにしてください。
まとめ
「睡眠が浅い」と感じる原因は人それぞれですが、原因を突き止め適切な対策を講じれば必ず改善の余地があります。
日々の生活習慣を見直し、睡眠環境を整えることで、少しずつ眠りの質は向上していくでしょう。忙しい現代人にとって睡眠はついおろそかにしがちなものですが、心身の健康を維持する上で質の良い深い睡眠は欠かせない基盤です。
ぜひ今日からできることに取り組み、毎晩ぐっすり眠れて爽快な朝を迎えられる生活を手に入れてください。睡眠の悩みが解消し、皆様の明日が今よりもっと元気で気持ちの良い一日になりますように。
本ブログの記事はAIによる作成です。亀屋家具が運営する当ブログでは、ベッドをはじめとした様々なインテリアに関する情報を提供しております。記事内容の正確性と有用性を重視しながら、最新のトレンドや実用的なアドバイスをお届けしています。皆様の快適な住空間づくりのお手伝いができれば幸いです。